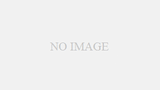人に会って、ずっと話を聞いていると、
どこかで自分の内側がすり減っていくのがわかる。
その場では、ちゃんと相槌も打つし、笑顔も出す。
でも、会話の波に合わせたり、
相手の感情を受け止め続けたりしていると、
じわじわと、自分の輪郭が薄れていく。
そんな日は、家に帰ると自然に手が伸びてしまう。
お酒に。
少しだけ気をゆるめたくて。
頭を空っぽにしたくて。
感情の輪郭をぼんやりさせたくて。
一杯目はたしかに効く。
ふっと気持ちがほどけて、
緊張がほどけて、
自分に戻ってくるような感覚になる。
でも、そこで止まらない。
二杯、三杯と続けていくうちに、
音楽もテレビもただのノイズになって、
気づけば、部屋の中には酒と自分だけが残っている。
「もう十分だな」と思ったときには、
身体は重く、気分は沈んでいて、
なんだかとても、くだらない人間になった気がしている。
翌朝は、たいていダメだ。
身体がだるく、頭もぼんやりしている。
なにより、何をしていても虚しい。
誰かと会って、疲れて、
その疲れをごまかすように酒を飲んで、
そのごまかしにまた潰される。
まるで、浅い穴を掘っては自分で埋めて、
また掘り返しているような気分になる。
そんなとき、ふと思い出す言葉がある。
「酒鬱」という言葉。
医学的なことはよくわからない。
でも、この言葉は妙にしっくりくる。
飲んだあとに襲ってくる、
説明のつかない自己嫌悪や後悔、
うまく言えない沈み込むような気分。
それを「酒鬱」と名付けた誰かがいたことで、
この重さを少しだけ、外に置いておける気がする。
たぶん、自分の性質として、
人に合わせると疲れ、
疲れると酒に逃げ、
酒で逃げると、また疲れる──
そういう循環があるのだと思う。
しかも、それをわかっていても、
抜け出せないときがある。
理想を言えば、
誰にも会わず、何にも揺らされず、
静かに、一定の気持ちで暮らせたら、それがいちばんいい。
でも、そんなふうに生きていける日は、たぶん、なかなか来ない。
そんなふうに自分の中で繰り返しているだけの、このやりきれなさに、
はじめて輪郭が与えられたような気がしたのが、「酒鬱」という言葉だった。
誰が言い始めたのかも知らない。
正式な用語でもないらしい。
でも、その言葉を見たとき、
自分の中にあった、うまく言えなかった気持ちが、
ひとつの名前に包まれたように感じた。
酒を飲むことを責めるでもなく、
感情の落ち込みを「気のせい」だと片づけるでもなく。
ただその状態に、
ああ、こういうふうに呼んでいいのかもしれない、と教えてくれた。
それだけで、ほんの少しだけ、
その沈みこみの中に、呼吸の通り道ができたような気がした。
「酒鬱」──
たぶん、それは飲んだあとに訪れる、
説明のつかない虚しさや自己嫌悪のための、
ひとつの居場所のような言葉なのだと思う。
私は酒をやめたいとは、あまり思っていない。
これからも、飲む。
でも、飲んだあとの自分を、前より少しだけ優しく見られるのは、
この言葉に出会えたからかもしれない。